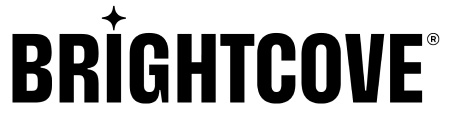2018年12月12日(日)、月刊誌「広報会議」編集長の森下育恵氏をモデレーターに、職場における動画活用セミナーを開催しました。日本マクドナルド株式会社 オペレーション&テクノロジー本部 テクノロジーアーキテクチャ&サービスマネジメント部(2018年12月12日現在)の四谷信行氏をお招きし、同社の動画活用についてお話いただきました。
今回は、日本マクドナルドの講演内容を紹介する。
## フランチャイズ・オーナーとクルーを含む従業員数は約14万人。
日本マクドナルドは直営店だけでなく、フランチャイズ方式の店舗も多く、FCオーナーやクルー(アルバイト含む)を含めた従業員数は約14万人。こうした従業員に対して、いかに戦略を徹底し、モチベーションを高め、巻き込んでいくかが同社の課題であった。
社内コミュニケーション強化の背景には、日本マクドナルドがさまざまな問題で一時業績不振に陥り、数年前から3週間ごとに新商品を発売する「Always On」という施策を実施していたことがある。
加えて、日本マクドナルドのクルー特有の問題が2つあった。
まず、日本マクドナルドのクルーの大半は学生であるため、卒業と同時に退職し、毎年約7万人のクルーが入れ替わる。第二に、近年は外国人クルーの割合が増えており、彼らは一般的に日本語での会話は問題ないが、読み書きが苦手な人が多く、漢字の多いマニュアルを理解するのが難しい。
## デジタル・コミュニケーションに注力
こうした課題を解決するため、日本マクドナルドは適切な情報手段(メディア)を使って従業員に情報を届ける施策を徹底した。具体的には、紙、スマートフォン、タブレット端末などの情報ビークルを用意したが、その中でもデジタルコミュニケーションに主眼を置いた。
スマートフォンやタブレット端末で閲覧できる社員向けの社内ポータルサイトを開設し、毎月の経営メッセージや社長からの営業成績の月次発表を動画で毎月配信したのだ。四谷氏は壇上で、動画の効果について「紙媒体だと読まれない情報が丸ごと読まれ、効果的な情報伝達ができた」と述べた。また、副次的な効果として、「紙媒体やプレゼンソフトを使っていたときに発生していた営業成績の外部流出が、動画を使うことで解消され、情報漏えいのリスクが減った」と述べた。
また、ハンバーグの焼き方、調理器具の手入れや洗浄方法などを動画にし、厨房内のタブレット端末で参照できるようにした。これにより、限られた時間の中で多忙な従業員に素早く情報を伝えることが可能になった。また、外国人クルーがマニュアルを視覚的に理解することも可能になった。
## チーム一丸の雰囲気を強めるのに役立った。
さらに、ビデオはチーム内の一体感の醸成にも大きく貢献した。
日本マクドナルドは、社内のモチベーションアップを目的に、社内イントラネットでダンス動画の投稿を呼びかけた。ダンス動画の見本を用意し、クルーが同じダンスを撮影して投稿できる仕組みを作り、クルーに動画投稿を呼びかけた結果、北海道から沖縄までほぼ全店舗から動画が投稿された。こうした動画を社内で公開することで、「ひとつのチームという雰囲気を強めることができた」と四谷は言う。
従業員に娯楽を提供することで、従業員は自由に楽しむことができる。双方向のコミュニケーションによって、社員のエンゲージメントをさらに高めることができることを示す社内コミュニケーション施策の一例である。
## 広報部門だけで社内の承認を得るのは難しい。
社内コミュニケーションは主に広報部門が考えるが、四谷氏は情報システム部門の協力が不可欠だという。セミナーでは、「広報部門だけで社内の承認を得るのは難しいので、情報システム部門が全面的に協力して企画書を作り、経営陣の承認を得るべきだ」という四谷氏のアドバイスは、情報システム部門ならではの視点だった。社員が様々なデバイス、様々な環境でいつでも情報にアクセスできるよう、社内コミュニケーションの準備の重要性を再認識したセミナーであった。