動画制作会社 90 Seconds Japanに聞く インターナルコミュニケーションにおける動画活用方法(前編)
Marketing
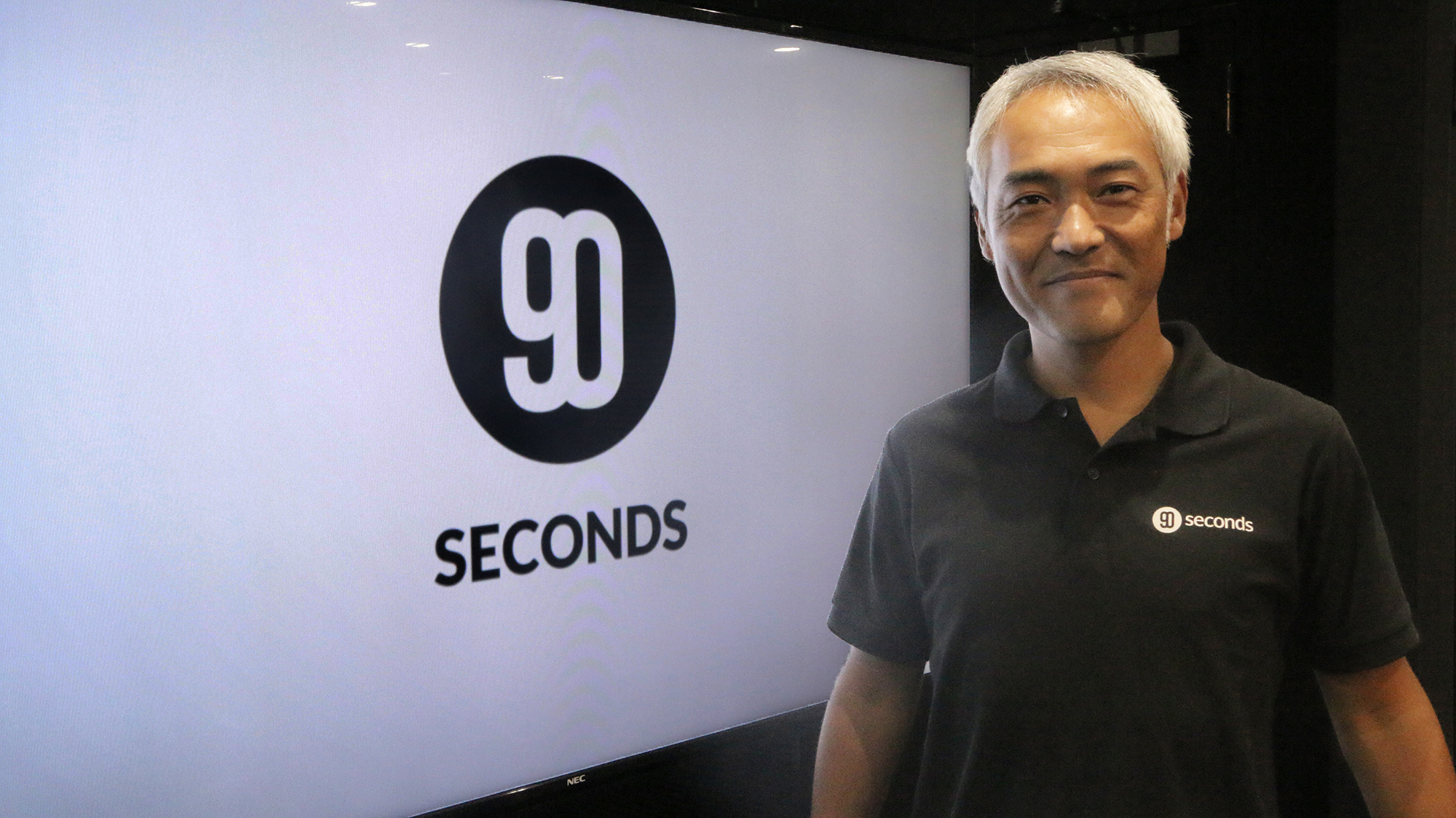
こんにちは、ブライトコーブ Business Development Managerの大野です。
近年、インターナルコミュニケーション(社内広報/コミュニケーション)において、動画の活用が注目されています。ブライトコーブにおいても資生堂様やオリックス様における動画活用事例を紹介してきました。一方で、これから動画を活用される企業の方々から、「どのような動画を制作すればよいのかわからない」や、「動画の制作方法を、社内外問わず誰に相談すればよいのかわからない」という相談を頂くことが多くあります。そこで、今回は動画制作会社 90 Seconds Japan株式会社 のセールスコンサルタントである滝本 龍志郎氏を訪問し、インターナルコミュニケーションにおける動画制作のヒントをお聞きしました。
【プロフィール】
90 Seconds Japan株式会社 セールスコンサルタント
滝本 龍志郎
2002年から映像業界のキャリアをスタート。営業プロデューサーとしてあらゆる業種、あらゆる種類の企業、官公庁の動画制作に携わる。フリーランスを経て2017年に90 Seconds Japanに参加。プロデューサーを経て現職。
企業規模が大きくなるにつれて、従業員間のコミュニケーションが不足
ブライトコーブ (以下 BC)大野 90 Seconds社とブライトコーブは、アメリカや日本で共催セミナーを実施させて頂くなどの交流がありますが、まずはどのような会社かお教え頂けますでしょうか?
90 Seconds Japan(以下 90)滝本氏 90 Secondsは2010年にニュージーランドで設立された、外資系の動画制作会社です。現在、世界8か国に拠点があり、日本法人である90 Seconds Japanは2014年に設立され、2019年現在、6期目になります。90 Secondsで独自開発したオンライン映像制作工程管理プラットフォームを活用し、全世界2万人以上の動画クリエイターと提携、160カ国、3,000社以上のクライアントで30,000本以上の動画制作実績があります。日本の企業においても、弊社のネットワークを利用頂くことで、国内だけでなく海外のクリエイターも利用し、簡単に動画制作頂くことが可能です。
BC 大野 インターナルコミュニケーションにおける動画制作についてはいかがでしょうか?
90 滝本氏 社内利用を目的とした、動画制作の依頼も頻繁に頂きます。背景として、企業の規模が大きくなるにつれて、従業員間・部署間のコミュニケーションが不足してしまうという慢性的な課題があるようです。そのため、「他部署がどのようなソリューションや製品を販売しているかわからない」といった課題を動画で解決できないか...という相談を頂きます。
動画がもつ情報量の多さ
BC 大野 そのような背景のなか、インターナルコミュニケーションにおける動画の価値とはどのようなものなのでしょうか?
90 滝本氏 動画がもつ情報量の多さです。『動き』『音声』『時間軸』の点においては、メールや社内報等の静的コンテンツに比べて、動画に優位性があります。
例えば、新拠点や新店舗がオープンし、その情報を社内に伝える必要があるとします。文字の場合、「**月**日に**駅近くに**平米の新店舗がオープンします」といったシンプルな情報になります。これを動画で伝えることで、駅からどの程度の距離があるのか、どの程度の広さなのか」、「何席あるのか」、「他にどのようなテナントが入っているのか」が臨場感をもって伝えられます。
展示会の様子なども動画で伝えることも効果的です。我々の顧客事例でも、海外の展示会を撮影し、従業員にその様子を動画で伝えられています。国内外問わず、従業員が自社の出展する展示会に参加できる機会は多くありません。どの程度の規模で、どの程度のブースを出展し、どの程度の来場者があったのかをレポートとして伝えるには動画が最適です。半日かけて書面のレポートを作成するよりも、カメラを持って展示会を撮影した方が、より多くの情報を伝えられますよね?
BC 大野 その通りですね。動画制作は大変というイメージを持たれている方も多いと思いますが、実際は動画によるレポートの方がスピーディーで、情報量が多いと思います。
90 滝本氏 今はスマホでも簡単に動画が作成できる時代です。やってみると以外に簡単だったりするので、動画制作=高度な技術が必要というイメージを払拭して頂きたいですね。動画には、他にもアーカイブとしての価値もあります。広報用に撮影した動画を、別の目的で転用できることがあります。
地理的に離れた各国の従業員が、お互いの業務内容を理解し合う
BC 大野 我々の顧客でもアーカイブとして再利用されている事例があります。実際の動画利用事例として、前述の新店舗オープンや展示会以外に、どのような事例があるのでしょうか?
90 滝本氏 事例を大きく分けると、『企業内の情報を共有する動画』と、『企業の経営メッセージを共有する動画』の二種類があると思います。新店舗オープンや展示会は、『企業内の情報を共有する動画』です。社内の規則やニュース、福利厚生施設の案内、新商品の説明、部活動の様子などを動画が該当します。
某消費財メーカー様では、新商品発表会の様子を撮影し、社内に共有しています。某携帯キャリア様では、販売店向けに新機種の仕様やセールスポイントを、アニメーションを利用して情報伝達しています。某精密機器メーカー様では、技術部門の新しい知識や技術を、営業や経営企画部門に伝えるために動画を利用しています。これらは、『企業内の情報を共有する動画』の好事例といえます。
また、日本に本社のある某大手機械メーカーでは世界各国にオフィスがあり、各国の従業員が自分の仕事を動画で紹介するという企画を実施されました。地理的に離れた各国の従業員が、お互いの業務内容を視聴することで、理解し合うという取り組みです。近年、我々の顧客から、このような動画制作の依頼が増えており、90 Secondsでは『Local to Local (LtoL)』と呼んでいます。
離れた場所に対して、正確性とリアリティを持って伝達
BC 大野 企業がサイロ化してしまうと、他部署や地方・海外拠点が何をやっているかを、従業員が把握できないという問題が発生します。動画を利用して各拠点(Local)が情報発信することで、従業員や部署間の相互理解や情報伝達が進むのであれば、動画が企業にとって非常に良い効果を生んでいると言えます。一方で、『企業の経営メッセージを共有する動画』の事例についてお話頂けますでしょうか?
90 滝本氏 はい。某化粧品メーカー様ではブランドメッセージを世界中の従業員と共有するために、動画を活用しています。某印刷会社様では、会社のデジタルシフトを従業員に周知するために、動画を利用していました。このような動画を90 Secondsでは『All Hands Video』と呼んでいます。海外では、経営者が全従業員を対象に情報伝達するミーティングを『All Hands Meeting』もしくは『Town Hall Meeting』と呼んでいますが、地方や海外に拠点・工場を持つ企業にとって、All Hands Videoは従業員の意識を統一するうえで有益な活用方法と言えます。
BC 大野 日本においても働き方の多様化が進み、他拠点化が進んでいます。また、海外の従業員は日本との時差があります。
90 滝本氏 その通りです。インターナルコミュニケーションに限った話ではなく、離れた場所に対して、正確性とリアリティを持って伝達できることが動画の優位点です。
前編は以上になります。動画制作会社ならではの目線で、インターナルコミュニケーションにおける動画活用方法や、事例についてお話頂きました。後編は、滝本氏に動画制作におけるヒントや注意点をお話頂きます。もっと詳しい話を聞きたいという方は、是非こちらから直接お問い合わせください!
